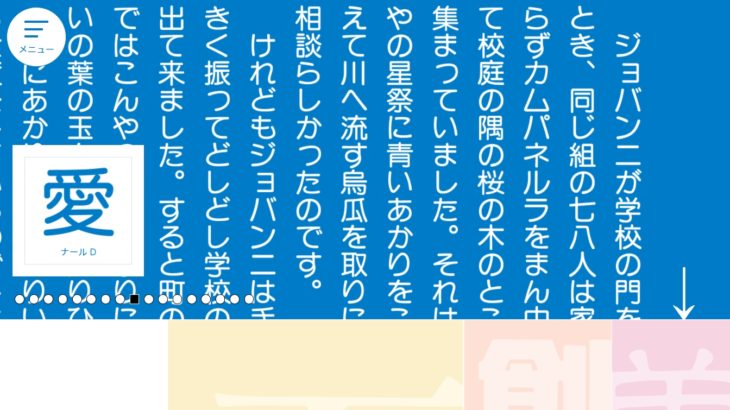「ナール」「ゴナ」など、数々の名フォントを輩出してきた写研。しかし、最近はあまり見る機会もなくなり、どちらかというとノスタルジーの対象となりつつあります。
写研の文字はDTPと呼ばれるPC上での書体割付作業ができないのですが、DTPに対応しないその理由は、どうも現社長のIT嫌いにあるから、ということらしいのです。
脱税(但し時効成立)・所得隠し及び粉飾決算を起こした1999年の読売新聞によると、社長の決裁なしでは社としての方針が決められないことが報じられています。
社長は会社の”法律”だった。(中略)
九三年に作成された社内分掌表が手元にある。「総務」「経理」「営業」「労務」「開発」ーー各部の責任者欄のすべてに社長の名前が記載されていた。
それは社長のゴーサインがなければ会社は動かない、ということを意味した。業界関係者の証言もある。
「写研さんは、社長がいいといわなければ何もできない。やれといわれたらどんなことでもやる」
出典:読売新聞『[隠蔽] 写研=中 「社長は法律だった」』(1999年1月3日,38面)
仮に社長のIT嫌いが事実であるとすれば、在任中は会社として絶対にデジタルフォントを出せないということになります。
モリサワのせいではない
熱烈な一部の写研信奉者には、「モリサワ社が模倣したから写研はダメになった!」と言う方がおられるんですが、決してそういうことではありません。
稀にこういう論調が見受けられます。
他人が考えて創ったものを「複製せずに作ったのだからオリジナルのデザインだ」と言い張り、そして利益を得ようとする倫理観のない作り手(※私の主観です)には対価を払いたくありません。ゴナを明らかに模倣して書体を作ること、そして使うことは、多くの労力と資金を費やして何もないところからゴナを作った写研や中村征宏さんが得られたであろう利益を奪い、侮辱する行為だと思うからです。
このデジタル時代に於いてこそ、「本物」を求めることが大切だと思うのですが……。出典:『書体のはなし ゴナ』http://ryougetsu.net/sho_unag.html
まず、裁判所で「模倣でない」と結審してる以上、モリサワ社を責めるのは筋違いです。
享受すべき利益を奪ったのはモリサワではなく、時代の流れを読めずにDTP化をいつまでも拒否し、みすみす機会損失を生んだ写研自身の責任でしょう。
写研社がこれまで、ナール・スーボ・ゴナなどのクオリティの高いフォントを多数輩出し、それに魅了されるのは理解できます。
が、(大阪に本社を置いてくれていることもあって)モリサワを貶めるような書き方はちょっといい気はしませんね。反論の意味も込めてこちらに掲載します。