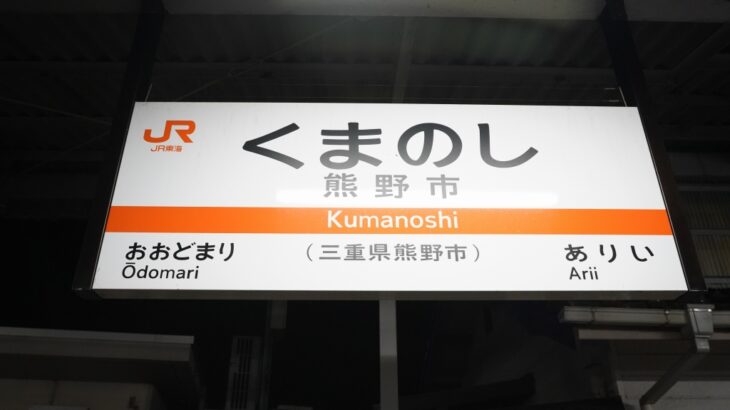鉄道関係の伝説エピソードを現在まとめています。
というのも「鉄道 伝説」で調べても出なかったり(そういう番組の名前が表示される)、体系的にまとめているページが見当たらないので、ここでは鉄道にまつわる様々な伝説を記載しました。
ここでは真贋がはっきりしなくても良いので、とにかくたくさんの鉄道の伝説を網羅したページにしています。
- 1. 真実
- 1.1. 「うるさいから103系を替えてくれ」と国に言われている
- 1.2. 783系が貨物列車を押した
- 1.3. 名鉄の特急電車がダンプカーを跳ね除けた
- 1.4. 布団が吹っ飛んで遅れた阪和線
- 1.5. 近江鉄道は新幹線建設の補償として景観料を要求した
- 1.6. 新幹線を作るとうるさくなる事の見返りとして作った埼京線。しかし埼京線の方(103系)がうるさかった
- 1.7. 223系はブレーキハンドルが折れたことがある
- 1.8. 列車トイレの導入は乗り遅れそうになって飛び乗りに失敗した人がいたから
- 1.9. キハ120形にトイレがついたのは女子高生が原因
- 1.10. 阪急電車が阪神へ殴り込んだことがある(物理)
- 1.11. 燕vs三条
- 2. お風呂を沸かすためにSLが来たことがある
- 3. 真偽不明
- 4. ガセ
- 5. 関連リンク
- 6. 今週の鉄道イベント情報
真実
「うるさいから103系を替えてくれ」と国に言われている
当サイトでも人気の伝説。「あんたが作ったんだろ」というツッコミはお約束。
783系が貨物列車を押した
こちらも人気の伝説。発生したのは2013年9月21日夜です。九州の特急は偉大ですな…
名鉄の特急電車がダンプカーを跳ね除けた

これも有名な話ですね。名鉄7000系はパノラマカーと車体前部が展望席になっていますが、ヘッドライト横にある油圧ダンパが乗客を守る仕組みになっています。
7000系の二つ名は「ダンプキラー」ですが、その名の通り踏切で立ち往生しているダンプカーをぶっ飛ばした事があります。
布団が吹っ飛んで遅れた阪和線

発生したのは2010年3月20日、読売新聞のネットサイトが報じています。
ちなみに布団が吹っ飛んで遅れるのは電車では割とよくある話で、東武東上線(2004年5月30日)、JR武蔵野線(2013年4月13日)でも同様の事例があります。
大阪府和泉市のJR阪和線では午後2時30分頃、沿線住民から「風で干していた布団が線路の方に飛んだ」と連絡があり、上下線20本に運休や遅れが生じた
出典:【社会】「ふとんが飛んだ!」干していた布団・洗濯物が線路に…電車止める – 大阪
YOMIURI ONLINE 2010/03/20[23:42:47]
近江鉄道は新幹線建設の補償として景観料を要求した
長年ガセとされていましたが事実のようです。というのも、国鉄の答弁記録にそういう証言があるそうです。
このあたりの詳細は大洋さんのブログにありますのでそちらをご覧ください。
新幹線を作るとうるさくなる事の見返りとして作った埼京線。しかし埼京線の方(103系)がうるさかった
これも事実。どちらかというと国鉄が約束を破った(民営化したので別団体のことになった)というのが真相のよう。
223系はブレーキハンドルが折れたことがある

中日新聞 2010年5月19日付にその記載があります。
列車トイレの導入は乗り遅れそうになって飛び乗りに失敗した人がいたから
一応実話ですが、トイレの設置自体はこれより前から始まっていました。
事故を受けてより設置が早まったというのが真相のようです。飛び乗りに失敗したのは宮内省御料局長官の肥田浜五郎という方のようです。
明治22年(1889年)4月27日、藤枝駅で走りはじめた列車に飛び乗ろうとして転落、負傷したため同地において療養するも翌28日午後1時卒去した。享年60。
当時の列車に便所がなかったため、駅で用を足した後、無理に戻ろうとしたためとされる[6]。同年中に列車内への便所の設置が始まっていたが、この事故も後押しした。
キハ120形にトイレがついたのは女子高生が原因

要因の1つではありますが、実際にトイレ設置の行動に至ったのは1万2000人の署名を持って浜田市の坂田議員が陳情に行ったことから。
よって真実でもあるしそれが全ての原因でもないという微妙なところ。
当初はトイレがついていませんでしたが、2004年から設置工事が行われました。
阪急電車が阪神へ殴り込んだことがある(物理)
「殴り込んだ」というのは新聞社の表現で、実際は意図しないものであったことから過失にあたります。
燕vs三条
140文字じゃ到底足りる内容じゃないのでこのwikiをご覧ください()
ざっくり言うと昔から仲の悪い隣同士の市が駅名を巡って相当揉めました() pic.twitter.com/LA6p2vheyF— 四ッ目 (@yotsume_1508) July 25, 2020
新潟県に位置する燕市と三条市はお互いが同規模の自治体で、駅設置にあたってはものすごい泥沼になったんだとか。
お風呂を沸かすためにSLが来たことがある

やってきたのはC59 111号機。
高松機関区のお風呂で使うボイラーが故障してしまい、急遽代用として山陽本線の電化で余っていた当機がやってきました。
高松機関区は1,000人レベルで人が働いている為、近隣の銭湯では代用が出来なかったのです。
1963年頃の話です。
蒸気機関車の台枠を流用したディーゼル機関車がいる
日本でなくイギリスでの話。LMS No.1831という機関車がそれに当たるそうです。
(情報提供:気まぐれソウさん)
真偽不明
はるかが小田急を遅らせた

真贋がはっきりしませんが、理屈上はありえる話。
そもそも終電で電車を待つ場合、定時で出したら乗客が一夜を明かさないとならないため、それにあわせて遅らせることがあります。ネットを辿ると2008年以前の話のようです。
他にも
・鹿児島線特急の遅れのせいで、新幹線→横浜線・東横線が遅れた
・常磐線の遅れを出雲市までひきずった
・はるかの遅れが、札幌近郊の通勤電車を遅らせた
・身延線の特急が遅れるせいで東京の中央線まで巻き添え
などがあります。
クロ683-1が車両製造所で衝突した

「サンダーバード」で使用されるクロ683-1号車が、他の683系トップナンバー車両と比較して1ヶ月遅れて竣工しているなどある程度の状況証拠はあるものの、実際にそれがあったかは不明。
こちらの動画を見るとわかりますが、本来だと6+3で9連の筈なのに、5+3の8連(先頭車1両が欠けている状態)になっています。
103系はトラブルが多発するので福岡市交通局がクレームを付けて地下鉄直通運用から外させた
真偽不明。
阪和電鉄の電車の警笛は柔らかかった
「柔らかい」というのは抽象的表現ですが、電笛であった可能性があります。
戦前の超特急「つばめ」は速さを維持するために走らせながら炭水車の隙間を通って行っていた
これについて詳しい話が『鉄道ファン』に載ってました。
1930年のダイヤ改正では C51(東京~名古屋)、C53(名古屋~神戸)の牽引で名古屋で5分停車、途中停車は基本名古屋と京都、補機連結の為の大垣・沼津・国府津のみで下りが9時間、上りが8時間55分を成し遂げたとのことです……— 黑鹿月/第漆術科師団 付 観測狙撃手 (@yukurokazuki) July 25, 2020
南海加太駅は日本軍の要請で集落から離れさせた
真偽不明。時期的にはマッチします。
南海北野田駅の南で急カーブしてるのは「鉄道が通ると若者が都会に出て不良になるから」
鉄道忌避伝説の一種でしょうか。ちなみにこれを言ったとされる美原町には現在も鉄道が通っていません。
近鉄田原本線は昔乗客が列車を押した
坂道を登れず、乗客が列車を押したという話。
非力な時代の鉄道では比較的よくある話で、明治期のの軽便鉄道などで同様の事例が見られます。
ガセ
近鉄奈良駅の地平時代は巨大な踏切
近鉄奈良や名鉄犬山橋や江ノ電や熊電の「併用軌道は踏切扱い」の件、鉄道趣味者による俗説であることを確信するに至った。運輸省通達や国会議事録や各社の社史等をいくら漁っても「踏切」の二文字はどこにも無く、併用軌道そのものとして取り扱っているものばかり。あとは俗説の発端を追えると良いなぁ
— うえぽん (@kaorurmpom) August 7, 2015
うえぽんさんが検証された結果、おそらくガセである(論拠が見当たらない)と結論づけられています。
前例が名鉄犬山橋から来ているものと思われますが、恐らく犬山橋についてもガセ。
近鉄奈良の長さ800mの踏切の都市伝説を斬る – togetter
https://togetter.com/li/875002