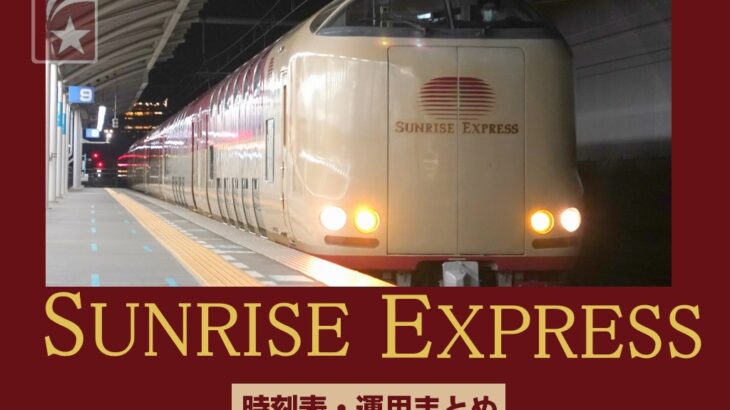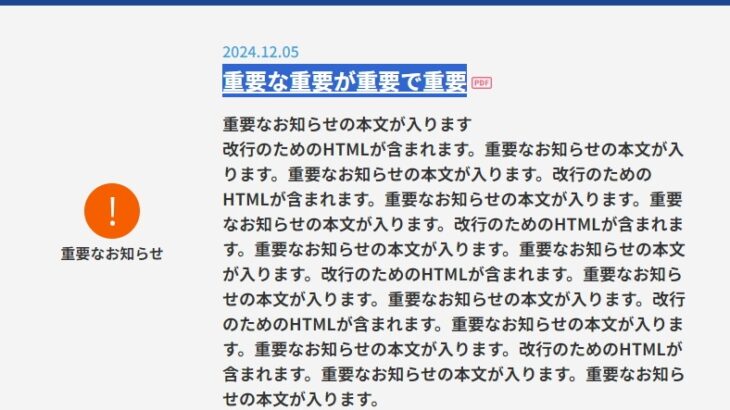名松線という鉄道路線があるのをご存知でしょうか。
三重県の松阪駅から北西の山奥へ進み、伊勢奥津駅までを結ぶJR東海のローカル路線です。
近畿圏であり近くを何度も通りながら、存在すら全く知らなかったこの路線。
先日「阪和線の沿線から」さんが訪れられたことに刺激され、私も行ってきました。
名松線とは

「名松(めいしょう)」という名前の由来は、松が生えているからではなく、名張と松阪を結ぶ路線として立案されたことが由来となっています。
当初はその計画通り松阪を起点に名張方面まで順調に路線を伸ばしていたものの、近鉄大阪線が名張⇔松阪間にて鉄道路線を通し、名松線を名張まで開業させる意義がなくなったことから、昭和10年に途中の伊勢奥津駅まで開業したのを最後に延伸されなくなりました。
2009年の台風18号では伊勢竹原~伊勢奥津間が被災したことで一旦は廃線が持ち上がりますが、三重県・津市とJR東海との交渉により、2016年に路線が復活しています。
伊勢奥津

スタートは終点の伊勢奥津駅から。起点の松阪駅から43.5kmポストにあり、名松線内では最も大阪へ近い場所に位置しています。

駅舎は2005年に新築され、比較的新しい建物。地元で採れた杉を利用しているそうです。
1935年開業当初の駅舎が長らく使われてきましたが、津市八幡出張所と合築の建物に切り替わり、地域コミュニティセンターと一体で予算計上されたものとみられます。

駅前の様子。1981年の文献には「商店街があった」との記載がありますが、今や見る影もありませんね…
(伊勢)奥津はこの地域(旧美杉村)の中心となる場所で、江戸時代には伊勢街道の宿場町として栄えたそうです。
近くには雲出川が流れ、周辺から産出される木材の港(津)が山奥に置かれたことから奥津と名付けられたのだとか。

伊勢奥津駅は1面1線の棒線式ホーム。
開業時は貨物輸送を行っていたこともあり3線を擁する広いホームでしたが、1965年に蒸気機関車から気動車へ切り替わり貨物輸送が終了したこともあり、2005年の駅舎新築時に縮小されました。
見えづらいですが、ホーム奥側には蒸気機関車時代に使われた給水塔が、現在でも蔦に覆われながら鎮座しています。

次駅の比津方面への眺め。ホームは花の匂いがします。

伊勢奥津駅は終点ということもあり、運転士さん用の詰め所が置かれていました。

そうこうしている内に、名松線を担当するキハ11-300形がやってきました。
2016年の運行復帰以来、この形式が専属で担当している他、列車検査時にはキハ25形がやってくることもあるそうです。
それまでは非ステンレスのキハ11形基本番台が担当していました

伊勢奥津駅の車止めとキハ11と。名張まで通っていればここからも線路が伸びていたんでしょうねぇ…
比津

伊勢奥津駅から1つ先にある比津駅にやってきました。

ホームは1面1線式。駅舎がやたらと綺麗ですが、2007年秋に建て替えられたのだそうです。
利用客が殆ど居ないような駅まで建て替えるとは流石JR東海。

ただ、トイレは……なかなか厳しいですね。配流設備が微妙なのか、駅はアンモニアの匂いがしてました…

JR東海「名所などない」

駅前には大量のソーラーパネルが並んでいました。ここに限らず、名松線沿線はソーラーパネルがたくさん並んでいるのが印象的でした
伊勢八知駅

比津から進んで伊勢八知駅に到着。

伊勢奥津駅と共に旧美杉村のもう一つの中心駅…とされています。
ただ、伊勢奥津駅よりも役所や学校など建物が点在している他、コンビニ(ファミリーマート)もあるので発展度合いはこちらの方が上です。

かつては交換可能駅で、駅舎の手前側に線路が分かれていたようです。

ここまで線路を見てきて思ったのですが、名松線は信号が全くなく、踏切用の非常停止信号のみが立っています。
これは後述する家城~伊勢奥津までを1閉塞としていることで、そもそも信号が必要ないことが理由です。
閉塞とは
鉄道における保安システムの一種で、「閉塞」と呼ばれる区切られたエリア内に列車を1つしか入れさせないというルールのこと。
一般的には信号がその役割を果たしていて、信号と信号の間を1閉塞とすることで、そのエリア内には他の列車が入れなく(赤信号にする)して衝突事故を防ぐ仕組みを取っています。

ぼーっと線路を眺めていると、キハ11形がトコトコやってきました。

村の中心だけあり、乗降客もちらほらいらっしゃいました
伊勢鎌倉駅

伊勢八知駅を出て、次の伊勢鎌倉駅に到着。いかにも簡易ホームといった感じの佇まいです。

元々駅をここに作る予定はなかったそうですが、地元の複数回に渡る陳情で鉄道省が方針変更し、駅が設置されることとなったそうです。

トイレは………なかなか厳しい…
伊勢竹原

伊勢鎌倉駅を出て伊勢竹原駅に到着。
名松線は1935年開業と国鉄線の中では後の時代に出来た路線なので、他駅との混同防止の為の「伊勢」の冠詞が続きます。

伊勢竹原駅は1935年に建てられた駅舎が未だに存在しています…!!!これにはちょっと感動

駅名表記部分もなんと右書きのまま。
御堂筋線と殆ど同い年の駅舎が未だ現役第一線で活躍してるのはすごいことですね

駅舎内の様子。こういうところでしか摂取できないものがね、あるんです

ホームは1面1線式。ここまでずーっとこのタイプですね。流石1閉塞。
家城

次の家城駅にやってきました

この駅はこれまでと違って、2面2線の大きなホームになっています!
名松線では唯一の交換駅で、松阪と伊勢奥津から出てきた列車はこの駅ですれ違うことになります。

家城駅は駅員が在籍していますが、これはこの駅で列車交換の為のスタフ閉塞を実施していることが理由です。
駅員もこの作業中は応対が出来ないため、切符販売ができなくなっています。

交換駅なので信号もちゃんとあります。名松線では珍しい存在です

伊勢奥津方面の様子。かつては腕木式信号機が使用されていたのだとか。
関ノ宮

ちょっとしたターミナル駅の家城駅を出て、次の関ノ宮駅に到着。

簡易的な1面1線式ホーム。スペースの狭さから後付けっぽい駅だなぁと思っていたのですが、その読み通り1938年の開業(路線の開業は1931年)でした
これまで山がちだった沿線ですが、このあたりから少しづつ街らしくなってきました。
伊勢川口

関ノ宮を出て伊勢川口駅に到着。まだまだ伊勢まみれな駅名が続きます

駅はまたしても1面1線でちょっと飽きてきました。夏らしい空のコントラストが救いです…

運賃的にはここがちょうど真ん中辺りのようで、松阪・伊勢奥津共に420円となっていました。
時刻表は2時間に1本で厳しい…

伊勢川口駅は保線車両の基地があるようで、名松線では珍しく側線が用意されていました。

かつては交換設備があった他、中勢鉄道という私鉄がこの駅に乗り入れていたそうです。

中勢鉄道は、この伊勢川口駅から久居を経由して岩田橋までを結ぶ 全線単線・非電化の私鉄でしたが、近鉄やこの名松線と競合する形となり1943年に廃止となっています。

伊勢川口駅近くで、2時間に1本のキハ11-300が軽快に通過していきました
伊勢大井

伊勢川口駅を出て、次は伊勢大井駅に到着。

またしても1面1線ホームです。ここから一志町に変わります。
駅横にはそれなりに交通量のある道路が通っているのみで、周辺は本当に何もありません。
信号も架線もないすっきりとした路線なので、一層際立ちますね…
井関


井関駅に到着。これまで紹介した駅の中では最も早い1930年の開業です。

駅は家城のようにかつてターミナルであったことを伺わせる作り。現在は1面1線ですが、交換出来るよう線路とホームがあったようです。

この不自然に曲がったカーブが複線だったことを伺わせます。

駅には6両停止位置らしき標柱もありました。ホームの長さもこの駅だけ長かったので、貨物の取り扱いがあったのかな…?
一志

最後の一志駅に到着。だいぶ都会になってきました

駅は相変わらず1面1線式ですが、周辺には人家が密集しています。
150mほどの距離に近鉄大阪線の川合高岡駅が位置していることから、そちらの乗降客によって発展してるようです。

駅舎はこれまでよりもちょっぴりグレードアップしたコンクリート式。

昭和43年12月建設とのこと。実はこの駅は昭和43年に300mほど移転して開設されており、その際に建てられたようでした

近隣には、「ベビースター」で有名なおやつカンパニーの本社が立地しています。
おわりに

名松線の旅、いかがでしたでしょうか。
名松線はこの先にも伊勢八太・権現前・上ノ庄・松阪と続くのですが、秘境でも都会でもない全く代わり映えしない風景に飽きてきたのと、夏の暑さが厳しくなってきたことでそれより先へは行かず、ここで引き返すことにしました。
名松線は、名張まで行かない中途半端さや自然環境による被災などから何度も廃止が検討されてきた路線です。
・赤字83線の指定
・特定地方交通線の指定
・2009年の台風被災による運休
しかし、その度に何度も地元の方の熱意によって撤回・復活がなされ、今日に至っています。
皆さんも是非一度足を運んでみてくださいね。18きっぷシーズンですので、夏休みの乗りつぶしにも最適かもしれません。
関連リンク
【元三洋電機の町】北条鉄道へ行ってきました
能勢電鉄の終点、大阪で一番北にある「妙見口駅」に行ってきました
北近畿タンゴ鉄道(丹鉄)に行ってきました【写真30枚】